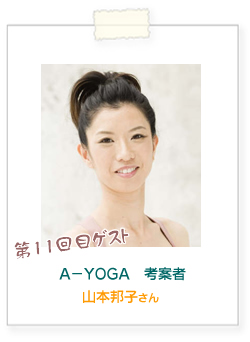
■第11回(2009.3)■
「A−YOGA」
〜 トップアスリートとの交流の中で生まれたYOGA 〜
◇PART2◇ part1はこちら
感じることで、人は強くなれる!もう、悲しい思いはしなくていい!
日本(人)が開発したプログラムをご紹介する「ジャパニーズフィットネス」第11回は、数多くのトップ・アスリートとの交流の中で生まれた「A−YOGA」をご紹介。その考案者、NATA公認アスレティックトレーナーであり、フィットネス事業アドバイザー、A−YOGA指導者育成などでご活躍中の山本邦子さんにお話を伺いました。
A−YOGA指導について
G(編集G):山本さんが実際にA−YOGAを指導されるとき、お客さまの身体に触れて修正またはサポートをする、アジャスト(またはスポッティング)を行いますか?
Y(山本邦子さん):一般のお客さまが対象の場合には、ほとんど行いません。逆に、アジャストが必要なほど大変なことになっているようであれば、自分の指示が不足していたのだと認識して、そこから修正や違う伝え方、自分の立ち位置を変えるなどしていきます。
 G: インストラクターやプロのアスリートでは一般の方と指導方法が違いますか? G: インストラクターやプロのアスリートでは一般の方と指導方法が違いますか?
Y:インストラクター養成コースなどでは、筋力もある方が多いですし、チャレンジさせると、みるみる動きが変わる方も多いので、アジャストを行うときもあります。アスリートには、ほとんどフローで(流れるように)教えることが多いですね。柔軟性としての柔らかさというよりは、「動きとしての柔らかさ」を必要としている選手が多いですので。
G:「動きとしての柔らかさ」ですか!プロの方は、やはりそういう感性がすごく秀でていますね。
インストラクターからよくある質問
G:講習会などをされていると、インストラクターの方からの質問を受けることが多いと思いますが、どんなことを聞かれますか?
Y:一番多いのは、ベテラン(?!)のメンバーさんと、初心者の方がレッスンに参加している場合、どちらを優先したらよいですか?という質問ですね。
G:やはりそうですか。どんなグループエクササイズ指導においても、迷いが生じやすいところなのですね。
Y:そうだと思います。これは、どちらかに合わせるのではなく、お客さまのアクションを見て、自分の立ち位置を変えたり、早めに判断したりすることが大切です。例えば、前屈の時にはあちらのお客様の近くへ行く、後屈ではこのあたり、初心者には手を添えて、ベテランさんには声で伝えていくということです。
G:つい、ぐらぐらしている初心者さんが目に留まるので、1時間ぴったりはりついてしまったということも起こりがちですよね。
 Y:お客さまのアクションに反応して、すぐにリアクションを返してしまうと、そういうことになってしまいがちかもしれません。こちらがきちんと伝わるように指示をしていないのに、また慌てて指示をしても、お客さまは混乱してしまいます。落ち着いて、全体を見て、違う方法で立て直す必要があるのです。 Y:お客さまのアクションに反応して、すぐにリアクションを返してしまうと、そういうことになってしまいがちかもしれません。こちらがきちんと伝わるように指示をしていないのに、また慌てて指示をしても、お客さまは混乱してしまいます。落ち着いて、全体を見て、違う方法で立て直す必要があるのです。
G:A−YOGAで大切にされている「感じる力」をお客様から引き出すポイントも教えていただけますか?
Y:はい。感じる力を引き出すには、どのボタンを押したらよいのかを探る必要があります。それには、人となりをとにかくよく見ていくことが大切です。ただ単にその人の外見やポーズの形を見るだけか、その人の身体になって体感しようと試みるのとでは、その後の判断と行動がまったく異なります。そうして初めて、この人はほっておいたほうがよさそうだとか、身体を動かすことで気づかせたほうがいいなとか、話をしたほうがよいなとかわかってくるんです。
 G:よく、コミュニケーションの極意は、相手の立場に立つとか、相手のして欲しいことをするといわれますが、その人の身体になって感じようとしてみるというのは、その究極のような感じがします! G:よく、コミュニケーションの極意は、相手の立場に立つとか、相手のして欲しいことをするといわれますが、その人の身体になって感じようとしてみるというのは、その究極のような感じがします!
Y:言い換えれば、身体を通じて人を見ているということです。相手を感じられないと、こちらが伝えたいことも届かないですので。
G:なるほど。これもよくある質問だと思うのですが、ポーズのバリエーションがないから飽きられてしまうからどうしよう・・・と。
Y:勝ったor負けたの世界ではないのですが、「また、同じポーズか・・」と思わせたら、指導者として負けだと思うんですよね。指導方法を変えたり、組み立て方を変えたり、ポーズがゴールではなく、その過程がとても大切だということを指導者が自ら示して、お客さまの可能性を引き出していくことに意識を向けることが重要なのではないでしょうか。
A−YOGA養成コース・今後の予定について
G:A−YOGA養成コースが 2009年4月末から東京と浜松で開催されるそうですね。受講日数は6日で、トータルの期間は約5ヶ月間というのは練習期間も含めてということでしょうか?

Y:そうですね。A−YOGAを指導するにあたり、まずは自分の身体を知る必要があります。そこをじっくりと取り組んで欲しいのと、同じように、お客さまにも長期スパンで取り組んでいけるようなサポートが必要だということを、体験して欲しいためです。
G:レッスンのたびにこのポーズが出来たor出来ないではなく、お客さまが本当に望んでいるカラダへ導くために、長期的な展望を視野にいれて毎回の指導を行うということを、まず自分が体感する必要があると。
Y:はい、クライアントを洞察する力を身につけて欲しいのです。養成コース受講生の中にもまれに、練習をせずに、要領よくきれいなポーズと流れのいいレッスンを作って帳尻あわせをしてくる方もいます。でも、それはすぐにわかってしまうんです。
G:そういう受講生がいたときにはどうされるのですか?
Y:まず、お客様がどんな気持ちでドキドキしながらレッスンに来ているのかを伝えます。そして、その方のその後の20年を考えて指導する大切さを、私の経験も交えてお話します。
G:その方の20年後!確かにとても大切なことなのに、意識をすることが少ないかもしれない・・・。私もこれから意識しようと思います!山本さんの印象と同じく、養成コースも静かに熱そうですね。
Y:私も、まだまだ日々勉強ですが、お客さまのことを考えるとつい受講生に厳しくなる時もあります。お客さまにとっては、最初に受講したレッスンによって、YOGAに対する印象や、お客さま自身に対する限界までも決めてしまうことになりますから。自分に対しても、お客さまに対しても、最初から可能性の芽を摘むようなことはして欲しくないんです。
G:インストラクターとの初めての出会いが与える影響力は大きいですものね。これからも、感じる力を引き出せるA−YOGA指導者が一人でも多く活躍されることを期待しています。本日は、お忙しいところありがとうございました。
Y:ありがとうございました。
part1はこちら
|